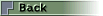チェルノブイリ医療支援活動に参加して
伊藤病院 佐々木栄司
原子力発電所爆発事故
1986年4月26日未明、旧ソビエト社会主義共和国連邦内ウクライナ共和国の原子力発電所が大爆発を起こし、その放射能は地球全体を被いました。発電所の名は『チェルノブイリ原子力発電所4号炉』(写真1)。爆発当時は強い南風が吹いており、放射性物質を多量に含む「死の灰」の約70%が、ウクライナ共和国の北側に位置するベラルーシ共和国に降り注ぎました。(資料1)
爆発事故のニュースを聞いた時は、私はまだ20歳の学生であり、テレビの中で久米宏キャスターが熱弁を振るっていた印象が今でも残っています。自分たち、いや、自分に直接降りかかった不幸とも考える事が出来ず、ただニュースを聞いているだけでした。その後、いろいろなマスメディアでもこの事故のことや被害を知る機会が多く存在していたにもかかわらず、恥ずかしながら、やはり自分にはあくまで「遠くの国の出来事」でしかありませんでした。
医療支援活動への参加
「チェルノブイリ支援運動・九州」(http://www.cher9.to/)という福岡県に籍を置くNGOがあります。このNGOは既にベラルーシ共和国内被災地への、6年間にも亘る息の長い医療支援活動等を続けており、その活動の1つに春と秋の年2回、甲状腺癌の増加していた被災地での甲状腺検診を実施しています。
私の医療支援活動参加への経緯ですが、現在勤務している甲状腺疾患を専門としている伊藤病院(東京都渋谷区)に、非常勤医師としてお越しいただいている永寿総合病院(東京都台東区)の片桐誠先生のお誘いによるものでした。先生はすでに1996年から年1回の割合でNGO「チェルノブイリ支援運動・九州」の検診活動に参加されており、3回目の支援活動からの、現地で採取された甲状腺の細胞診標本を日本に持ち帰られ、その標本を私の病院で染色し、診断のお手伝いをさせていただいていました。片桐先生は、甲状腺細胞診の現地での迅速な対応と染色技術や細胞診断法の普及が必要だと考えられ、2000年春のこのNGOの7回目(ご自身の参加5回目)の検診活動から甲状腺細胞診のできる検査技師を伴うことになりました。このような経緯から、私に白羽の矢が立ちました。
2000年と2001年の6月中旬からの約2週間、現地医療支援活動に参加させていただきました。1986年のから既に15年経過しているチェルノブイリの原発事故は、このようにして私の身近に感じる出来事となりました。
ベラルーシ共和国ってどこ?
ポーランドの東、ロシアの西、バルト3国の南、ウクライナの北。そこにベラルーシ共和国があります(資料2)。今なら言えますが…。これまではベラルーシ共和国のある場所さえ知りませんでした。
検診に赴く場所は、放射能汚染濃度の高いブレスト州ストーリン地区でした(資料3)。日本からの直行便のないベラルーシへはフランクフルトまでで1日、フランクフルトからベラルーシの首都ミンスクまで1日、ミンスクから一般道で約500Km離れたストーリン地区まで車で1日と、検診場所までは日本を出発してから3日を要して辿り着く場所でした。
ベラルーシ共和国の甲状腺癌の現状
「ミンスク甲状腺悪性腫瘍センターベラルーシ赤十字委員会」がまとめた資料を参考に、ベラルーシにおける甲状腺癌の現状を説明いたします。この資料は、「チェルノブイリ支援運動・九州」が発行している通信紙(No,51)に掲載されており、解説は同NGOの検診活動に何度も同行された「広島甲状腺武市クリニック」の武市宣雄先生が書かれたものであり、通信紙から抜粋し、ここに載せさせていただきます。
資料4、5の表とグラフでわかりますように、事故後0−14歳の小児甲状腺癌が急増しています。それまでのベラルーシでは小児の発生率は、年間人口100万人に対し1―3人であったものが、事故後3―4年で急激に増加しはじめ、数十倍に上昇、ピークは10年後の1995年でした。甲状腺の放射線感受性は小児に高いということが指摘されていましたが、悲しくも指摘内容が実証される結果となりました。このことは、すでに武市先生が1991年に予測されていました。
2002年4月26日以後、年齢15歳以下の小児は、原発事故後に生まれている事になります。近年、0−14歳の甲状腺癌発生率が減少している事実から、原発事故で放出された放射性ヨウ素は半減期が8日と短いため、原発事故後に生まれた子供への影響が少ないという結果がうかがえます。
しかし、一方で1996年以降、年々急上昇している16―18歳の思春期を迎えた子供たちのグラフがあります。事故当時、1―3歳だった子供の甲状腺癌発生率を示すもので、1995年には10万人に対し、3.8人だった発生率が2000年には9.5人の割合まで増加しています。
実際の小児期の甲状腺癌患者数ですが、私が検診に参加したブレスト州と、最も多くの放射能が降り注いだゴメリ州の発生数が多いです(資料6)。小児甲状腺癌の数値は年々減少しているものの、16―18歳の思春期の発生数はグラフのように増加しているのが現状です。事故後15年という時間の経過は、新たな放射能の影響を起こし始めているのです。
ベラルーシ及び検診地域における医療事情
検診の現地医療スタッフの中心は、ミンスク第10病院の内科医師と国際赤十字所属の医師からなっています。国立再教育センター(ミンスク第10病院)のラリサ教授は、「経済的問題により医療面の質が下がっており、若い医師たちを教育するための資材などが不足している。手術後の患者が必要とする甲状腺ホルモン剤も継続的に供給されず、時期的には不足し、医師が日常的に使用する器具でさえも不足している」と語っています。
首都のミンスク(写真2)でさえこの様な状態なのに、まして地方では、アルコールや染色液さえままならないのが現状です。現地には日本から全ての器具,染色試薬を持っていき、検診に臨みました。検診システムは、あらかじめ国際赤十字所属の医師たちが移動検診で患者を選出し、ブレスト州ストーリン地区の内分泌センター(写真3)で我々日本の検診団の診察を受けることになっていました。
現地で細胞診の普及しない理由としては、先に述べた慢性的に物資が不足している事情に加え、共和国自体の医療体制にも問題があるようにも思いました。というのは、国内の赤十字団体等の検診を受けて腫瘍が見つかった患者さんは、直接ミンスク第1病院(ミンスク甲状腺癌センター)(写真4)へ運ばれます。その結果ベラルーシ共和国の腫瘍統計は極めて正確なものになります。しかし、反面、地方で詳しく診断しようとしても出来ない状態が続き、次に述べるような悪循環を招いていると感じました。
検診地区スタッフの意識
検診に参加した最初の年、私の仕事は検体処理と染色、時間に余裕があれば細胞像の鏡検指導まで行う事でした。いざ、パパニコロウ染色を開始し染色法を現地スタッフに伝えようとした際、スタッフの1人から「患者さんはミンスクに行くから、ここで細胞診はしないし染色もしない。だから、私たちは覚えなくても良い」といった内容の言葉が出ました。検診の際、現地スタッフからは、私たちの「補助業務に徹しよう」とする姿勢はあるものの、彼らからは、「自分たちの危機感」を感じる事が出来ませんでした。
私の口から次の言葉が出ていました。「この染色は細胞診の分野では最も代表的な染色であり、細胞の特徴を理解するのに極めて有効である。今はこの地区に必要はないかも知れないが、今後,甲状腺の細胞診を始めるのなら絶対に覚える必要がある。だから、今、覚えなさい!これは命令だ!」。その後、染色法は熱心に覚えてくれたものの、「何故、必要なのか?」を根本から理解してもらうまでの時間は足りませんでした。結局、最初の年は検診活動に追われるのみで、教育的部分の指導があまり出来なかったことが、強い反省として自分に残りました。「チェルノブイリ支援運動・九州」の代表である矢野宏和さんに「この地域には細胞診断する医師がいない事が一番の問題であると感じる。診断する医師がいなければ必然的に地方で細胞診は施行されない。」医療物資を補助するのも1つの支援だが「甲状腺疾患を細胞診で診断するんだ!」という強い気概を持つ医師を育てるような人材育成も1つの支援ではないかと伝えました。
私の中の意識変化と講義
2回目の参加となった2001年6月の検診活動では、前年、検診地域の医療関係者に伝えられなかった“細胞診の重要性”というものをどのような方法で伝えるかを考えました。「自分に出来る事から始めよう」と日本から多くの講義用スライドを持参して臨みました。検診合間のわずかの時間や、宿舎になっているホテルに戻ってからと数回ですが講義をすることが出来ました。(写真5)
先にも述べましたが、地方で腫瘍が認められた患者は、首都のミンスクに送られます。そのミンスク甲状腺癌センターでさえ、術前の細胞診断が明確でない為に、たとえ良性の腫瘍であっても甲状腺全摘術を受けるような現実がありました。そもそも細胞診は悪性疾患を見つける為の手段ですが、良性の腫瘍など手術をしなくてもよい症例をフォローする為の手段でもあります。検診ではどうしてもガンを見つける方が重視されがちですが、本来はむしろ良性を良性と診断できることに大きな意味があります。細胞診がこの地で根付くことは、すぐに施行しなくともよい甲状腺の摘出術が減少することにつながるのです。平均月収が約50USドルという経済状況下で、交通網の不便なベラルーシでは地方からミンスクに出て診察を受けるだけでも半月分以上の給料は吹っ飛びます。甲状腺を全摘された患者さんは一生ホルモン剤を飲み続けなくてはなりません。患者さんの経済的負担はかなり大きいものがあるのです。だからこそ「自分たちが染色し診断する細胞診」を中央から地方の検診場所に至るまで、早急に根付かせる必要があるのです。そのことを少しでも地方スタッフに意識して欲しく、まず“一歩前へ”という気持ちでいっぱいでした。
これまでの成果
NGOや検診団の行動は、現地に根付く活動でなければ、唯の自己満足に陥りがちになる可能性を多いに含んでいると言えます。昨年9月に起きた同時多発テロの影響から、2001年秋の10回目の検診活動は中止されました。しかし、過去9回にわたっていっしょに検診活動を続けた結果、現地医師たちだけでチームを組み、10回目の検診に当たったのです。昨年まではエコー像のみの検診をやっていた医師が、今年は細胞診までやれるようになったと聞きます。「継続する事が大切!」と改めて感じました。支援活動で大切なのは、物資の援助だけでなく「教育」であると強く感じます。
この頃思う事
つい先日までの日本は、アフガン復興支援国際会議でのNGOの取り扱いが論議を呼んでいましたが、NGOの草の根的活動を多くの日本人が知る機会がもっとあればいいと考えます。知らない所で細胞検査士を含めた多くの日本人が、多くの団体とともに活動していると思います。職場の環境などから参加できない方も沢山おられると思いますが、幸いにも私は、伊藤公一院長を始めとする職場の皆様の理解があればこそ2年続けて参加できたものであり、「チェルノブイリ支援運動・九州」の皆様、また、バックグランドにおられる多くの皆様のお陰で本当に良い経験をさせていただきました。支援活動に参加したことは自分を再発見することにもつながり、これによる意識の変化を今後の自分に生かしていきたいと思います。この場を借りて改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。
この稿を終えるにあたり、一言お伝えしたい事があります。この原稿を書いているときに、大変悲しく、ショッキングな知らせが届きました。私が2度にわたって参加した際、現地スタッフとの通訳等でお世話になったミンスク第10病院の内科女性医師であった、カテリーナ・カプスチーナ医師が12月26日に生まれたばかりの愛娘タチアナさんとともに、産休中の1月25日にガス中毒で亡くなられました。享年28歳でした。熱心な先生だったことから「チェルノブイリ支援運動・九州」では今後、教育的バックアップの対象者と考えていた矢先の出来事だったそうです。細胞診も積極的に学ばれていたのを思い出します。誠に残念で仕方がありません。ここに改めてお二人のご冥福をお祈り致します。